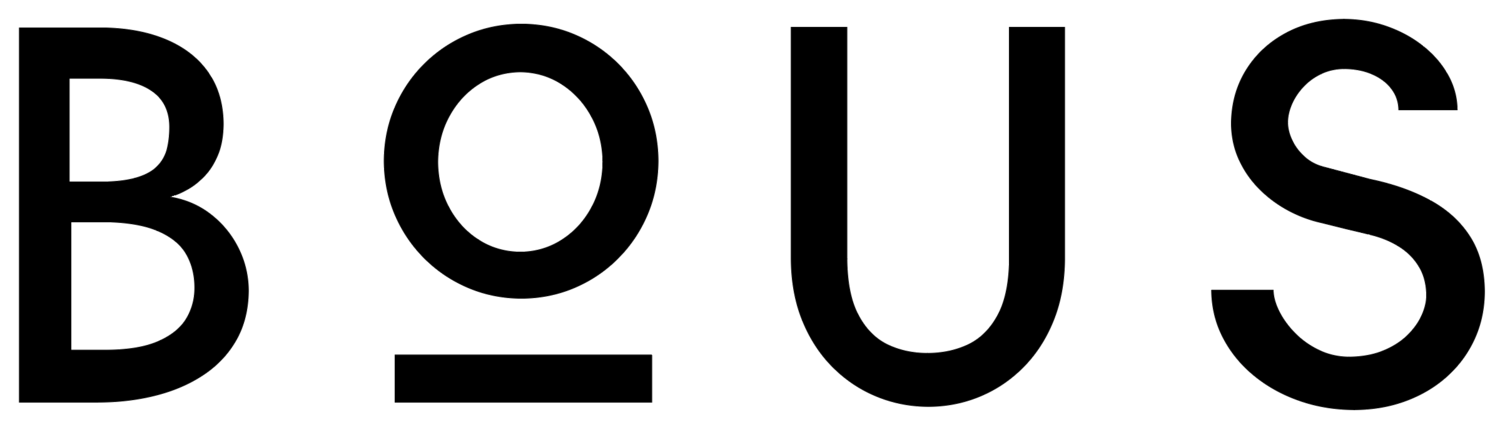ターゲットCEO辞任と関税の影響:ウォルマートの戦略から学ぶ米国小売業の現在地
はじめに
2025年8月、米国大手小売チェーン Target(ターゲット) のCEO、Brian Cornell氏が退任を発表しました。3四半期連続で続いた売上低迷と利益率の悪化が大きな要因とされていますが、背景には米国の関税政策の影響も無視できません。一方で、同じ小売業界のライバルである Walmart(ウォルマート) は、関税負担が重くのしかかる中でも堅調な業績を維持し、むしろ消費者を引き寄せています。
本記事では、ターゲットとウォルマートの事例を比較しながら、米国小売業界における関税政策の影響と今後の展望を解説します。
目次:
1. ターゲットCEO辞任の背景
2. ウォルマートはなぜ業績を維持できているのか
3. 関税政策が小売業界に与える3つの影響
4. まとめ
1. ターゲットCEO辞任の背景
1-1. 売上不振と収益悪化
ターゲットは3四半期連続で売上減少を記録。
在庫調整費用の増加や値引き競争により利益率が圧迫されていました。
さらに一部商品の品揃え戦略をめぐるボイコットも影響し、販売力が弱体化。
1-2. 関税が与えたコストインパクト
トランプ政権下で進む対中関税の強化やデミニミス制度の廃止により、ターゲットが扱う家具・家電・日用品の仕入れコストは大幅に上昇。
特に、中国や東南アジアから輸入する低価格商品の価格競争力が低下し、利益を圧迫する要因となっています。
2. ウォルマートはなぜ業績を維持できているのか
ターゲットが苦戦する一方で、Walmart(ウォルマート)は逆に関税の影響を巧みに回避しています。
戦略1:サプライチェーンの多様化
ウォルマートは、中国依存度を早期に下げ、ベトナム・メキシコ・インドなどのサプライヤーと連携。
特に鉄鋼・家電・家具分野で、関税影響を最小化する調達網を構築。
戦略2:価格競争力の維持
関税コストの一部を消費者価格に転嫁しながらも、大量仕入れによるスケールメリットを活かし、ターゲットよりも安定した低価格を提供。
戦略3:食料品・必需品での強み
ウォルマートは食料品の売上比率が高く、関税の影響を受けにくい構造。
生活必需品を軸とすることで、インフレ下でも消費者の支持を維持。
3. 関税政策が小売業界に与える3つの影響
(1) デミニミス制度の廃止
2025年8月29日から、800ドル以下の商品でも関税免除が適用されなくなり、越境EC・低価格帯製品に大打撃。
ターゲットのように低価格雑貨・家電を扱う企業には特に痛手。
(2) 中国製品への高関税
中国製品には最大50%の関税が適用されるケースもあり、家具・鉄製収納シェッドなどの価格に大きく影響。
調達先を多様化できない企業ほどダメージ大。
(3) 利益率圧迫による戦略見直し
サプライチェーン再編、国内在庫増強、価格戦略変更など、各社はコスト吸収と消費者価格維持のバランスを模索中。
4. まとめ
ターゲットとウォルマートの事例から、日本企業が米国市場で取るべき戦略のヒントは次のとおりです。とりうる可能な戦略を実行しつつ動向を見極める必要があります。
(1) 戦略内容効果調達先の多様化
中国一極依存から、ASEANやメキシコを含む複数国サプライチェーンへシフト
(2) 米国内在庫の活用
3PL倉庫・フルフィルメントセンターを使い、関税負担を軽減
(3) 関税分を考慮した価格設計
価格体系を見直し、仕入れ段階でのコスト転嫁を検討
(4) 製品カテゴリ選定
関税影響を受けにくいカテゴリー(必需品、食品、衛生用品)への注力
参考:
Target hires a veteran as its new CEO, as it tries to turn itself around. Some say the move lacks ‘pop.’ - MarketWatch
Walmart wins customers over Target as tariffs lead to higher prices - The Washington Post