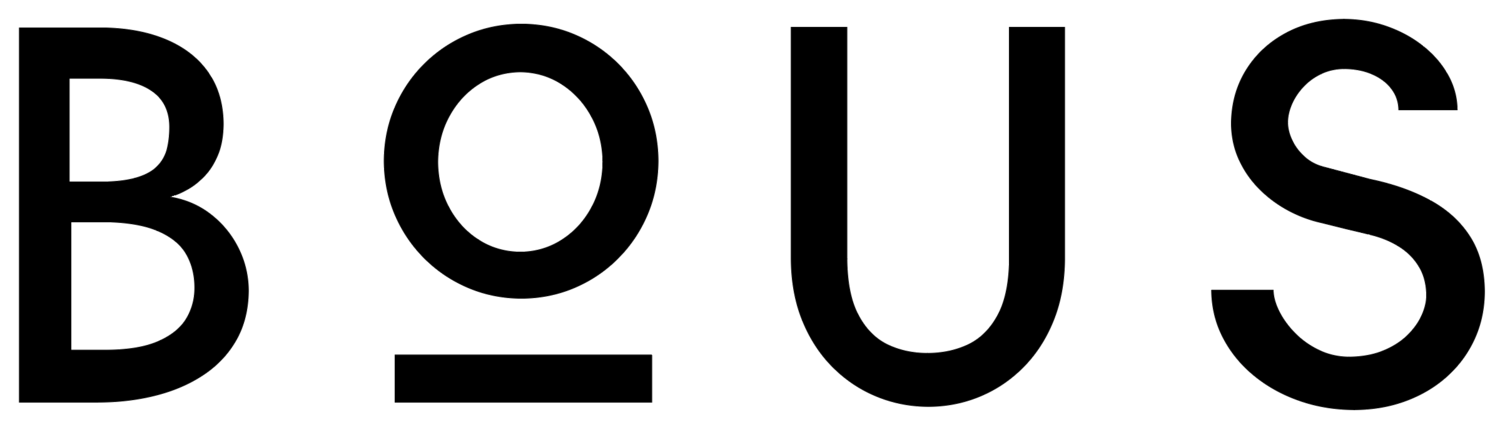日本ブランドが現地の消費者とつながる方法〜ポップアップとイベント活用術〜
アメリカ市場で日本ブランドが成功するカギは「体験」にあり。先日BOUSでも出展を行った Little Craft FestやChicago Stationery Festの事例を交え、ポップアップイベントを活用した現地消費者とのつながり方と販売・ブランディングのポイントを解説します。
目次
なぜアメリカでは「体験型販売」が重要なのか
ポップアップの種類とメリット
イベントの選び方と準備のコツ
まとめ:販売とブランディングを兼ねた効果的な施策
1. なぜアメリカでは「体験型販売」が重要なのか
近年、オンラインショッピングやサブスクリプションサービスの普及により、消費者はいつでもどこでも商品を購入できるようになりました。 一方で、デジタル化が進めば進むほど「リアルな体験」や「人とのつながり」の価値が再評価されています。
特に最近のアメリカの消費者は、
実際に手に取って試したい(品質や使い心地を自分の目と手で確かめたい)
ブランドのストーリーや思いを知りたい(購入体験の中で感情的なつながりを求めている)
同じ趣味・関心を持つ人とつながりたい(コミュニティとしての参加を楽しむ)
というニーズを強く持っています。そのため、リアルイベントやポップアップは、単なる「商品販売の場」ではなく、ブランドと消費者、消費者同士のコミュニケーションとコミュニティ形成の場 として非常に重要なのです。
2. ポップアップの種類とメリット
単独開催
ブランドの世界観をフルに表現できる(例:ライフスタイル提案型のショールーム形式など)
一方で、集客力と告知がカギになるため、SNSやメールリストなどの事前マーケティングが不可欠
他ブランド・他社と協業
類似ターゲットを持つブランドと組むことで集客を補完
コラボレーションによる話題性アップと新規顧客獲得
マーケットイベント(Little Craft Fest、Chicago Stationery Festなど)
既にコアファンが集まるため、高い確率でターゲット層にリーチ可能
他のベンダーとの差別化(日本ブランドの本格的な品質やデザインを伝えるチャンス)
ワークショップやスタンプラリーなど、体験型コンテンツが用意されており、ブランド体験の深度を高められる
Little Craft Fest 2025 では、3000枚のチケットが完売し、スタンプラリーやワークショップによる「楽しみながら文具に触れる体験」が消費者との接点となり、大きな熱気を生みました。
大盛況だったLittle Craft Festの様子
満員電車のようだったChicago Stationery Fest
3. イベントの選び方と準備のコツ
イベント選びのポイント
ターゲットとする消費者層(年齢、趣味、購買動機)とイベント来場者層が合致しているか
小物やクラフト系商品が中心のイベントなのか、本格文具やライフスタイル雑貨も受け入れられる場なのか
商品ラインナップの最適化
ステッカー、マスキングテープ、キーチェーンなど「気軽に買える」「コレクションしたくなる」アイテムは人気
一方、万年筆やノートなどは、「書き心地」や「使い方」をデモすることで興味を引きやすい
現場での工夫
商品を手に取って試せる「体験型展示」を意識する
スタッフが商品の魅力を丁寧に説明できるようにする
来場者とのコミュニケーションを楽しむ姿勢を持つ
SNS・プロモーションの連携
イベント前のティーザー投稿、当日のライブ感ある投稿、事後のシェアなどでイベントを最大限に活用
イベントのSNSは会期半年前くらいから発信を開始し、イベントやベンダー情報、限定商品などの情報を配信。https://www.instagram.com/littlecraftfest/
5. まとめ:販売とブランディングを兼ねた効果的な施策
ポップアップやイベントは、単なる販売の場ではありません。
現地消費者と直接会話をし、商品を体験してもらう機会
SNSや口コミを通じたブランド認知拡大のチャンス
イベントを通じたロイヤルカスタマー(ファン)づくり
という3つの大きな役割を果たします。
デジタル時代だからこそ、「リアルでのつながり」が消費者にとってより価値のあるものになっています。
アメリカ市場においては、このようなリアル体験をうまく活用し、ブランドの存在感を高めていくことが、今後ますます重要になるでしょう。